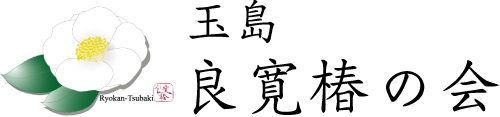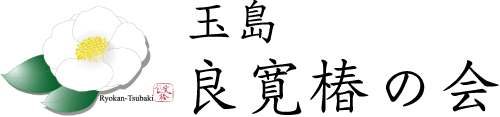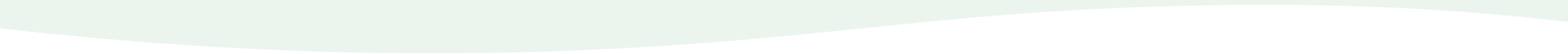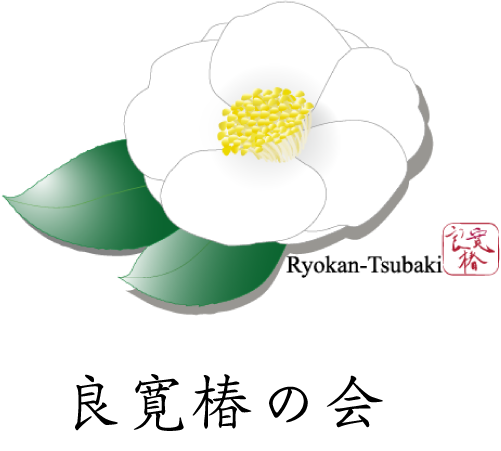『はちすの露』を初めて読んだ。病床の良寛さんを最後に看取った、貞心尼の書いたものだ。良寛の死後、5年して、表した作という。死後、時間が少し経ち、いわば、貞女のこころに、良寛との思い出が純化され、自ずと現れて来たもの、それを素直に表した書といえる。
この書の最初のあたりは、良寛の和歌が、出てくる。それらを書き残したい気持ちから書き始めたのか、とさえ思えた。書の後半には、良寛と貞心尼の相聞歌が、まるで交換日記のように現れてきた。これを、書かざるを得ないほどの熱い想いが、ふたたび、貞心尼の心に現れてきたのだろう。
そう思わせるほど、二人に相聞の和歌に、惹きつけられる。いつの時代でも、恋する人の気持ちの中に生まれる炎を、二人は感じているのが伝わって来た。良寛さんも、こんな気持ちになったのだと思うと、何となく、ほっとするものがあった。例えば、こんな嬉しさである。
「天が下にみつる玉より黄金より春の初めの君が訪れ」
良寛さんは、雲水の道を求め、生涯を歩んだ。ご存知のとおりだ。その生涯での、外への発揚は、詩歌や墨跡であった。それらは、今も、私達を惹きつけて止まない力を持っている。良寛さんが、これほどの広がりを持っている何よりの証だ。
晩年には、子供達と手まりをついて時を過ごしたり、酒や囲碁すら、交遊ある人々と交わす事もあり、いっそう親しみをもたれる良寛。しかし、一人にかえれば、常に、心の道を求める、孤絶な精神の持ち主だった良寛さんである。畏敬すべき人でもある。
その彼の心に目覚めた、ときめきを私は二人の唱和に感じる。最晩年になって、初めて、女性に恋する心が動いた。その驚きを、彼は、胸に感じ、かみしめていたに違いない。肉体の衰えは、いかんともしがたい。しかし、二人の唱和には、ただよっている熱い魂のさざ波がある。歓びがある。
いかにせむ学びの道も恋草の繁りて今はふみ見るも憂し(貞心尼)
いかにせん牛に汗すと思いしも恋の重荷を今は積みけり(良寛)
恋は、生涯、道を求め続けた人間良寛への、仏さまのごほうびだったのかもしれない。