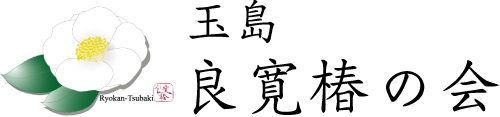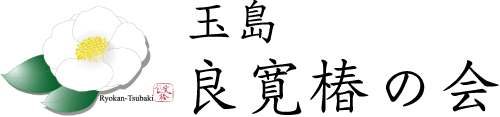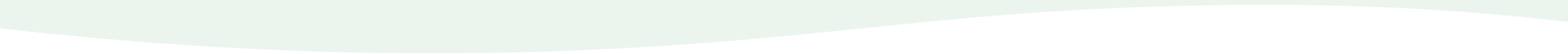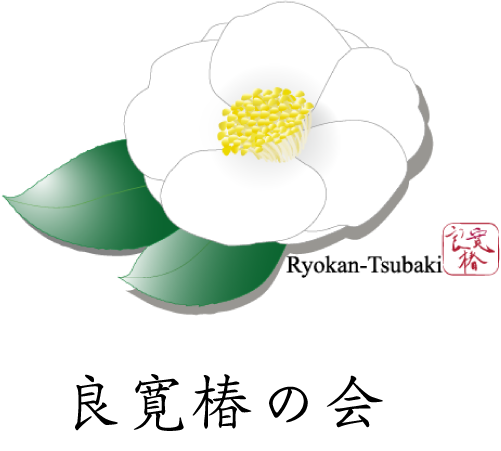「首を回らせば七十有余年 人間の是非 看破に飽く」と言う言葉が、『草庵雪夜作』の中にある。人間や人の世を考えぬき、生きて来た。それにも、飽きてきたという言葉に引っかかる。良寛にしては、少し、なげやり感のある言い方だ。そんな事を、ある日感じた。良寛の長歌を再び読んだのは、そんなときだった。そこに見いだしたのは、今まで、気がつかなかった、良寛には、めずらしい、哀感や悲嘆であった。
良寛は、長年の間、孤独な草庵生活の中でも、世の中や宗教界を見つめ批判し、激しい言葉を漢詩の中に閉じ込めてきた。その背後には、精神の緊張や、透徹した眼差しがいつもあった。しかし、悲嘆、つまり、自己の悲しみや苦しみを嘆くことは、なかった。それが長歌の中には、散見されるのである。(『良寛歌集』吉野秀雄 校註・平凡社1993年)
長歌には、良寛の晩年の心情が、実にたくさん露出している。歌における情の面では、貞心尼との思い溢れる唱和がある。『はちすの露』に、見られるこころである。それに加えて、晩年の長歌に散見されるのは、良寛の哀感に満ちた心情である。良寛も、やはり、一人の老人としての、老いの苦しみや哀しみを味わっていたのだ。
年齢を重ねると、自他ともに分かってくる事の一つは、自分の肉体の老いる実感である。さらには、それに伴って生じるもろもろの病気である。体がマイナス状態に成れば、必然的に、心のエネルギーも弱く成って行く。
それは、人の生み出す作品にも現れざるを得ない。良寛の長歌に見えるのも、そういう、情緒や、うずきのようなものだ。
ひさかたの 長き月日を いかにして 世をわたらむ 日に千たび
死なば死なめと 思えども 心に添はぬ たまきはる 命なりせば
かにかくに すべのなければ こもりいて 音のみし泣かゆ 朝夕ごとに
(前掲書・和歌番号1242)
このような悲哀あふれる言葉を連ねてゆく良寛の姿はかってみられなかった。この悲嘆を何と言えばよいのか。一人の人間として、老齢を迎え、それを実感し、死を向うに見ながら生きて行かねばならない人間の宿命が、そこにはある。これを、長歌に現したところに、良寛の近代性もあるのか。