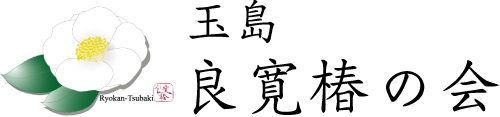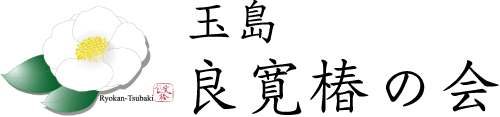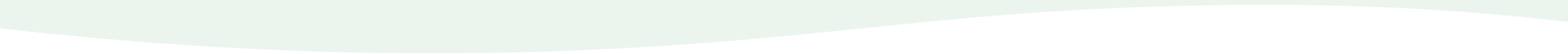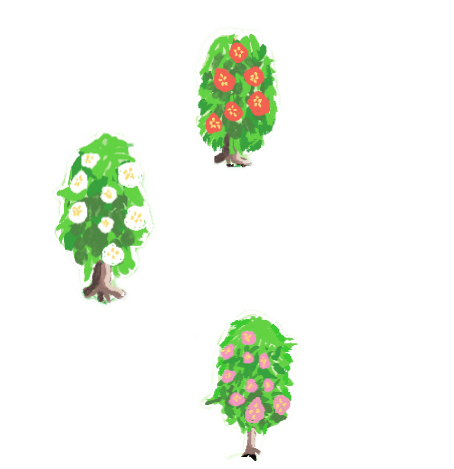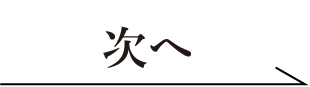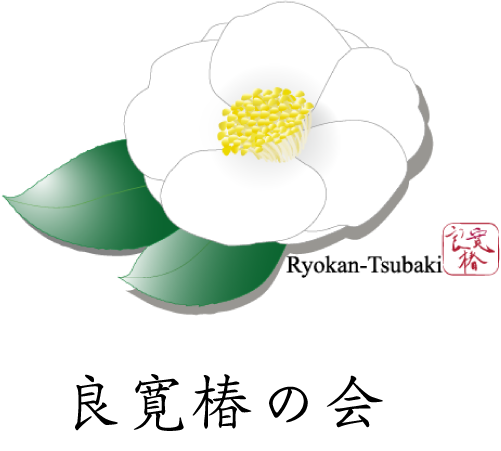良寛の秋の歌をくりかえし読むと、その時々に、
この季節、つまり、秋を歌う短歌には、
あはれさは いつはあれども葛の葉の 裏吹き返す 秋の初風(288)
秋の野の草むら毎に おく露は 夜もすがら鳴く 虫の涙か(359)
秋の野をわが越え来れば朝露にぬれつつ立てりをみなえしの花(
草や花の一瞬の姿の、とても細やかなところに、
また、良寛の心音を奏でている歌には、こんな作もある。
訪ふ人もなき山里に庵して ひとりながむる 月ぞわりなき(314)
先きに、良寛は、「耳の人」でもあったと、書いたが、
あしひきの山田のくろに鳴く鴨の声 聞く時ぞ 秋はくれける(542)
秋の歌の中には、良寛さんが、紅葉を歌う短歌もかなりある。
うらを見せ おもてを見せて 散る紅葉