
長谷川洋三氏の、『良寛禅師の真実相』(木耳社刊)
この著書を読んでいて、まず、思うのは、
研究とは、まず、その対象の真実を追求し、そのためには、
この著書は、多くは、良寛の「漢詩」が考察の対象となっている。
例えば、長谷川氏が、一つの漢詩をとりあげて論じる場合、
その論の、持って行き方に、私は、説得され、感服する。
長谷川氏は、著書の中で、一貫して、「良寛禅師」
まだまだ、読み進まねばならないが、途中での感想を言えば、
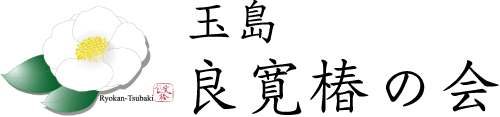
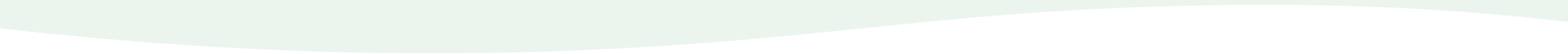
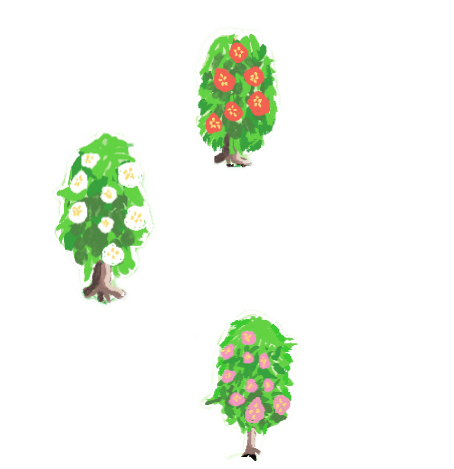

長谷川洋三氏の、『良寛禅師の真実相』(木耳社刊)
この著書を読んでいて、まず、思うのは、
研究とは、まず、その対象の真実を追求し、そのためには、
この著書は、多くは、良寛の「漢詩」が考察の対象となっている。
例えば、長谷川氏が、一つの漢詩をとりあげて論じる場合、
その論の、持って行き方に、私は、説得され、感服する。
長谷川氏は、著書の中で、一貫して、「良寛禅師」
まだまだ、読み進まねばならないが、途中での感想を言えば、