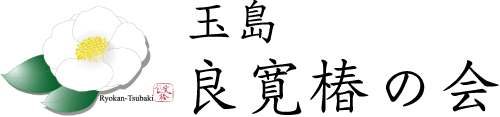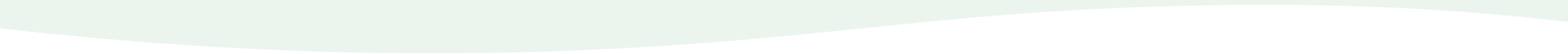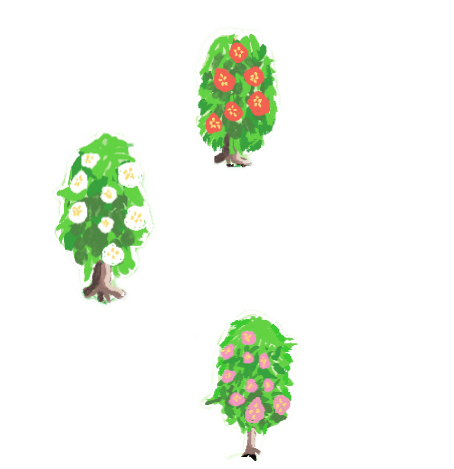良寛さんは、不思議な人である。あれほど孤立した生活を送りながら、私達に与える印象は、決して孤独性ではない。ほっこりした、あたたかみのあるものを与えられる。現在の社会に、最も必要なものを内に秘めている。
知識人、小説家、詩人、また、良寛を研究する人達は、むろんのこと、私のような庶民にいたるまで、良寛さんほど、現在、親しまれている人は珍しい。現実に生きている人ではないから、なおさらである。皆さん、いかなる事を契機として、その良寛さんへの親愛は生まれ、育っているのであろうか。
私の読書の範囲では、中川省一氏の、良寛さんについての色々の著書に見られる傾倒に、心打たれた。この頃は、長谷川洋三氏の著書から受ける、學者としての姿勢や良識に、敬服する想いが、生まれている。
一人の人間が他人様の心を惹き付け、信頼を生み、信仰されるまでの存在に成る。宗教の始まりは、それであろう。
良寛さんの場合、そのような宗教の祖とは成ってはいない。しかし、現在を生きる人々のこころを捉え、これほどまでに広がりをみせている。良寛さんは、もう、「良寛宗」と形容出来る程の祖の存在になっている。
祖を離れて祖に帰る。良寛のことを考えると、そんな感懐を持ってしまう。若き日に、大忍・国仙和尚に出逢い、玉島の地に出奔、その後、師の下、円通寺での十二年間の禅の修行。しかし、国仙の死を契機として、寺を去った良寛。その心の奥に秘められていた決意は、何だったのか。祖を離れて、祖に帰る、細い道だったのではあるまいか。
良寛は、心の髄から、宗教の人である。ただ、良寛には、まれにみる「詩魂」が、資質として備わってもいた。恐らく、父、伊南から受け取ったものだ。
この詩魂によって生み出された、漢詩、和歌、書等によって、後世の人々は、更に感銘を与えられる宝を持つ事に成った。