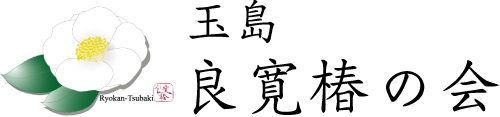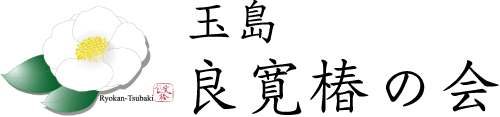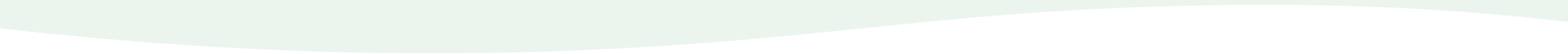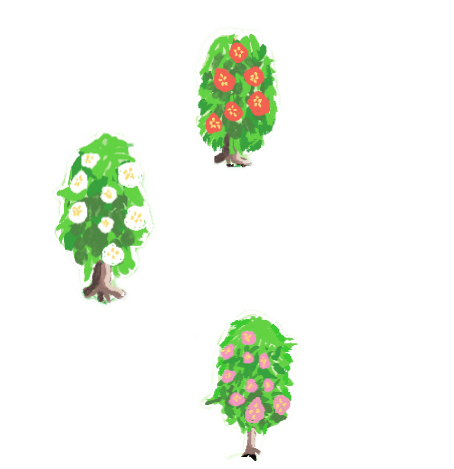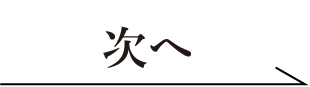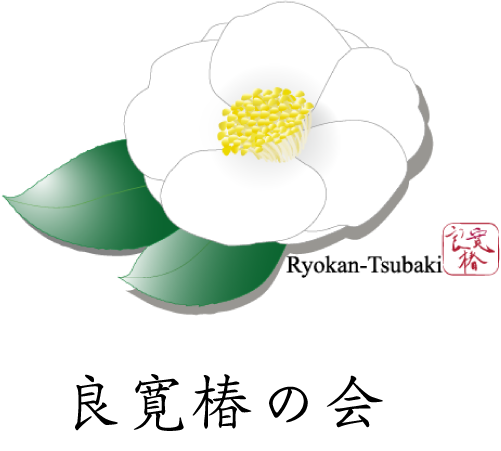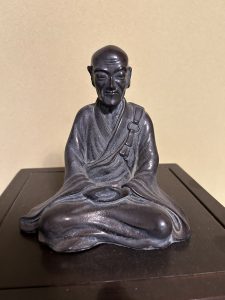 実際に交流した人が、日常生活の上で感じ取った、良寛さんとの色々の体験や話が、豊かに見いだせる本を読んだ。解良栄重の著した「良寛禅師奇話」である。「奇話」とは、現代語で言えば、エピソードであろう。彼が、この文を書いた動機を、次のように、つづっている。
実際に交流した人が、日常生活の上で感じ取った、良寛さんとの色々の体験や話が、豊かに見いだせる本を読んだ。解良栄重の著した「良寛禅師奇話」である。「奇話」とは、現代語で言えば、エピソードであろう。彼が、この文を書いた動機を、次のように、つづっている。
師 平生ノ行状詩歌中具在ス 今又比ニ贅セス 其逸事ヲ記スルノミ
この著作の全体では、「六十」の「逸事」が書かれている。右の文は、その「四十九」番目である。(訳文―師の常日頃の行いは、詩や歌の中に具体的に語られている。ここでは、そこにあるようなことを書いて紙面は使わない。ただ、知られていない話を記すだけである。)
この著作の解説と訳文は、馬場信彦氏である。氏も述べられているように、この著作の動機は、右の言葉につきる。
この本を読んで、私が、心を動かされたのは、「六」に記された逸話である。
師 音吐朗暢 読経ノ声 心耳ニ徹ス 聞者 自ラ信ヲ起ス
(訳文―師の声は朗らかでのびのびしており、お経を読まれるとき心の奥底まで達する。これを聞く者は 自ずから信仰の心がおきるのである。― 馬場訳)
声という最も身近な機能で、人の心を打つものを、良寛さんが持っていたという証言である。聴く者は、御経の内容までは、わからなくとも、その声の響きを聞けば、調声によっては、人物の信仰すらわかるし、さらには、庶民に、帰依させる力すらあったことが伝わる。人柄は、日常生活で付き合っているうちに、自然に、感得されてゆくものである。
この著作の中には、よく知られている、童らと戯れる良寛さんや、有名な竹の子と厠の話も載っている。「五十」には、良寛の亡き後、その顔が数日たっても威厳ある、凜とした死に顔であったなどとも書かれている。また、「六十」には、良寛が、若き日に師の国仙和尚からいただいた「喝」の言葉を、死の床でも、肌身離さず、ふところに抱いていた、などの事を読むと、感動を覚えざるを得なかった。良寛さんに、じかに会っているような錯覚すら感じた。
読まれることを勧めたい、一冊である。 (8/2・2025)