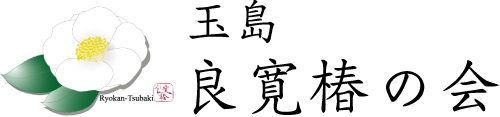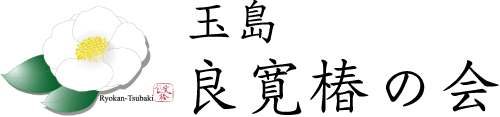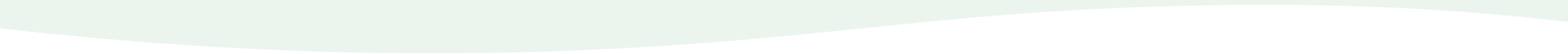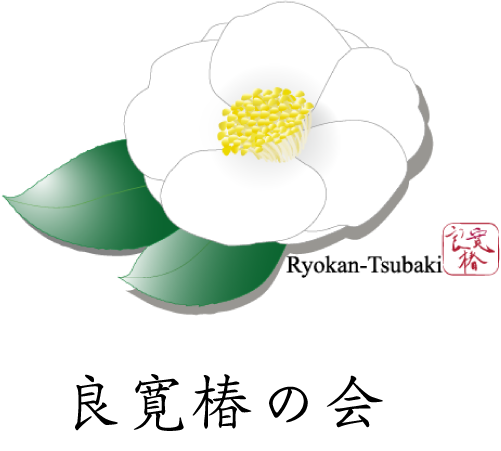円通寺の国仙和尚様のことを語られるとき、良寛様の眼には、いつも、涙が浮かんでくる。それほど慕われていた方が、入寂されてしまった。良寛様は、新しい和尚様が寺に来られるとともに、やがて、円通寺を去られる決心を、された。その折の、心中を察すると、辛い気持ちになる。
円通寺の国仙和尚様のことを語られるとき、良寛様の眼には、いつも、涙が浮かんでくる。それほど慕われていた方が、入寂されてしまった。良寛様は、新しい和尚様が寺に来られるとともに、やがて、円通寺を去られる決心を、された。その折の、心中を察すると、辛い気持ちになる。
その時の良寛様のお心は、「悟りをうるまでは、必ず、厳しい修行を、一人で続ける、と深く、国仙和尚様に誓っていました」というものだった。そう、おっしゃられたのは、二人で縁側に座り、夕日を眺めていた時だった。
「あの夕日のように、温かく輝く、人を和ませてくれるもの、それをつかみたくて、もがきました」とも、おっしゃられた。
円通寺での修業時代、良寛様は、他のお坊様方とは、どこか同感できない、孤独な自分を、いつも感じておられたそうだ。本性として、孤立せざるを得ない資質を、持っておられたのだろう。孤高の魂を、お持ちの方なのだ。
四国を行脚されている時、懐に抱いておられたのは、中国の賢人莊子様の書物だった、と聞いたこともある。
荘子さまは、あるがままの自然を、そのまま受け取り、その中で、なお、道の探究をしてゆくという、考えをもっておられた方だった。そういう方を道しるべの一人としての孤独な修行が、どんなにか厳しいものであったか。わたくしには、到底、及びもつかない、日々であったろう。
ただ、求道の日々であっても、日々の糧は、手に入れなくてはならない。托鉢に、家々を、回られていたことは、間違いなかろう。訪れれば、その昔、空海様が、お導きなされた土地柄の人々は、遍路をする人達のように、迎えてくれたことも、しばしば、あったのだそうだ。実に、ありがたかったと、良寛様は感謝を口にされた。
一夜の宿を、田舎のお寺に、求められたことも幾度となくあった。
「しかし、病に陥ったときが、やっぱり、一番つらい、思いをしました」
「そんな時は、どうなされたので、ございますか」とおたずねすると、
「仏様のお慈悲で、必ず、助けてくれる方に出会うのです。あるいは、古い御堂が、見つかったりしたのですよ」
いつものように、額に手をやりながら、良寛様は、笑って言われた。
村の衆が、たまたま通りかかり、見つけてくれ、御堂まで、おむすびを、持ってきてくれた。また、女衆が、看病さえしてくれた時もあった。そんな時には、仏様は、必ず見ていられる、と思わざるを得なかった、とおっしゃった。
「貞心どの、仏様は、衆生の中に、生きていられるのです」と、しみじみと、言われたこともある。あの一言は、今でも、心に残っている。
あるお寺にお参りになられた時は、その寺の和尚様と話すと、なぜか気が合って、誘われるまま、数ヶ月も逗留された由。寺の一角にあった、古い御堂に住まわせて、おもらいになった。
そういう事への見返りには、寺の作務を一緒にやられたり、檀家の法事にも、同道されたりしたこともあった。
そして、夜になれば、一人、灯火の元、古の仏典や、荘子などを、読みふけられた。そんな探求の修行が続き、孤独な旅は、数年続いたのであった。
そんな修行中に、いつも、心に抱いておられたのは、やはりあの、「悟りの一言」への願いであった。
 円通寺の国仙和尚様のことを語られるとき、良寛様の眼には、
円通寺の国仙和尚様のことを語られるとき、良寛様の眼には、