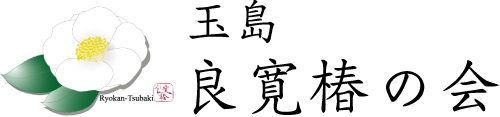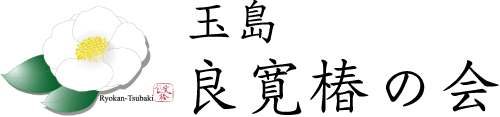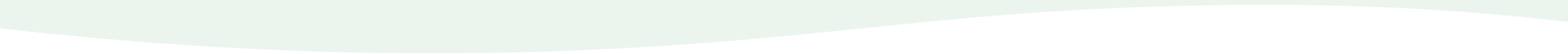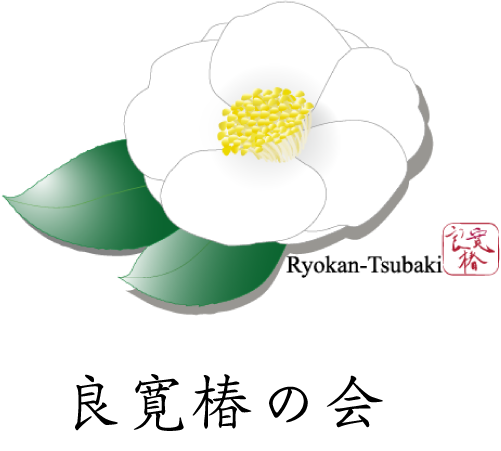あれは、何度目かに庵を訪れた時だった。良寛さまは、もろ肌脱いで、縁側にすわり、お体を拭いていらっしゃった。夏の間近に迫った、暑い日だった。
あれは、何度目かに庵を訪れた時だった。良寛さまは、もろ肌脱いで、縁側にすわり、お体を拭いていらっしゃった。夏の間近に迫った、暑い日だった。
「これは、しつれい、いたしました」良寛さまが、笑いながらおっしゃった。
「わたしこそ、庭先から勝手にまいり、ご無礼を、いたしました」
とっさに、そんな言葉が、口をついてでた。
「おふきいたしましょう」わたしは駆けより、わらじを脱いで、縁に上がった。
「お任せしようか」良寛さまは、そうおっしゃりながら、手ぬぐいを桶につけ、絞られてから、わたしにお渡しになった。はいと、いって、それをうけとった。
良寛さまは、背中から見ると、がっしりした骨太のお身体だった。頑丈な物がでんと、そこにあるような気がした。首筋までは、赤銅色だった。でも、そこから下の、背中や腕は、真っ白だった。そのあまりの違いに驚いた。やはり、長年の托鉢生活のせいで、顔や首筋は、日焼け、なされていたのだろう。
最初にお目にかかった時には、赤銅色のお顔をなされていた。カラスほどは、黒くないけれど、やっぱり、黒いという印象だったのを思い出す。
わたしは、肩に、左手を乗せながら、上から背中を拭き始めた。お肌は、きめ細やかだった。まるで、女の肌のような、艶があった。
わたしも女だから、昔々、若年で、嫁に行ったときには、こんな肌をして、夫につかえたものだ。あれから、何十年か、経っているけれど、男の人の肌を、また、拭くことがあろうとは、思ってもいなかったことだった。
 あれは、何度目かに庵を訪れた時だった。良寛さまは、
あれは、何度目かに庵を訪れた時だった。良寛さまは、