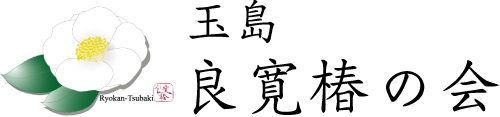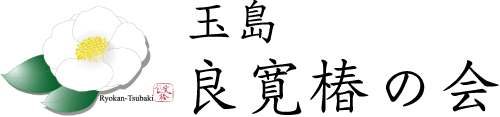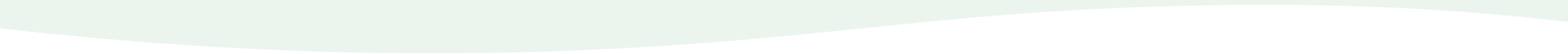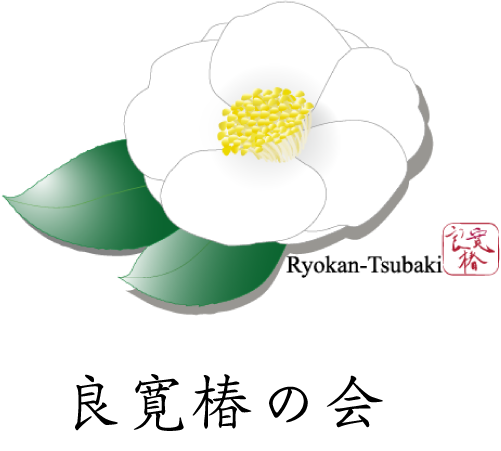良寛さまのことを、考えていると、お声の独特なことにも、ふと気がついた。あのお声に早く接したい、そんな気持ちになるのだ。
良寛さまのことを、考えていると、お声の独特なことにも、ふと気がついた。あのお声に早く接したい、そんな気持ちになるのだ。
読経をとおして、それが実現したのは、解良様のご本家の仏事があった時だった。日頃、お世話になっている方でもあった。お声をかけていただいたので、わたくしも出かけた。良寛さまも、当然、来ていらっしゃった。皆様と、お座敷でお茶をいただきながら、少しお話をしていると、やがて、準備ができたのか、お女中が、皆様を呼びに来られた。
わたくしも、皆様の後に続いた。お部屋の真ん中に、黄金に輝く、立派な御仏壇が、据えられていた。良寛さまは、すでに、仏壇に向かって、右のお席に、座っていらっしゃった。わたくしが、お座敷に入る時、お茶を、お召し上がりになられているところだった。
わたくしは、良寛さまのお姿が見たくて、つい、視線を向けた。そのとき、丁度、良寛さまも、ちらっと、わたしの方に、お顔をあげられた。心臓が高鳴った。視線の先で、良寛さまが、黙礼されたように感じたのは、わたしの錯覚であったろうか。皆様も、お座りになり、沈黙がお座敷に広がったときだった。
良寛様は、「では、始めましょうか」と、一声おかけになって、立ち上がられた。そして、真ん中に置かれた、厚い座布団にお座りになった。背筋を、ぴーんと、伸ばされていたせいか、後ろから見ると、五十を、超えたくらいのお姿にさえ見えた。がっしりした体躯でもあった。
良寛さまと、お話しするときは、朗らかな感じがしていたお声が、御経を、読まれ始めると、何か、違った人の声に響いてきた。わたしは、その心の中まで、入ってくるようなお声にびっくりした。
解良様が、後年、良寛さまの逸事を、諸々書かれた中に、良寛さまのお声は、「心耳」にまで届き、信仰する気持ちにさえなると述べられていた。まさにその通りであった。やはり、解良様も、同じことを良寛さまの声に、お感じに、なっていらっしゃったのだと思った。
御経の声は、わたくし達に、直接、お声をかけていらっしゃるようにさえ、思えたものである。読経がすべて、おすみになると、わたしは、心の中まで、洗われたようにさえ思えた。不思議であった。
皆様のお顔にも、それが現れていた。
どこで、あのような技を、身につけられたのであろうか。いや、そんな言い方は適切ではないだろう。技などというものではない。やはり、良寛さまの深い信仰から、生まれてくるものが、わたくし達の心にまで沁みてくるのだ。ありがたいことだと、つくづく、皆さまも、お話しになった。心をうごされたゆえ、お声のことばかりを、書いてしまった。
仏事が終わると、別のお座敷には、お膳が準備されていた。
「さあ、良寛様、皆さま、お部屋の方へお越しくださいませ。ささやかでありますが、古人を忍びながら、一献、いただきましょう。良寛様の大好きな、越後の銘酒も、そろえてありますゆえ」と、ご主人がおっしゃった。その瞬間、お座敷に、大きな笑い声が響いた。良寛さまが、お酒も大好きな事を、誰もが、知っていらっしゃったからであった。
良寛さまは、打って返すように、「では、一献、いただくことにしますか」と、おっしゃった。お座敷には、また、笑いがこだました。
お座敷に入り、わたしは、末席をしめようとした。すると、「貞心尼さま、こちらへ、おいでくださいませ」と、ご主人がおっしゃった。どうしたものかと、一瞬、戸惑った。その時、良寛さまが、「貞心尼どの、こちらへ、来られれば、よかろう」と、明るい声で、おっしゃった。わたしは、「はい」と答えて、そちらへ行った。
あの日は、本当に良い仏事が営まれた。古人が、生活の中で、皆様と、親しくしていらっしゃったことが、とても良くわかった。
良寛さまが、後でお話になった、解良家のこと、古人のことなどを伺うと、良寛さまが、どんなにか、解良様に対して、感謝の心を持っていらっしゃるかも理解出来た。良寛さまのお口から出る言葉に、みなさまも、うなずいておられた様子であった。やはり、良寛さまは、仏の道を究めていられる方だと、今更ながら、心が動く思いであった。
良寛さまは、お酒を召し上がるにつれて、とても、上機嫌にもなられていった。真剣に、御経を朗唱されるときとは違い、童にも、お女中たちにも、慕われるお姿になられていたのだった。
この方は、どこまで、懐の深いお方だと思わざるをえなかった。また、庵を訪ね、わたくし一人で、お話を聞きたいとさえ思った。
 良寛さまのことを、考えていると、お声の独特なことにも、
良寛さまのことを、考えていると、お声の独特なことにも、